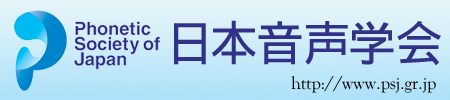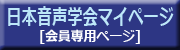- 申込方法:
下記の URL より申込用紙をダウンロードし,所定の事項を記入の上,日本音響学会までファクシミリ又は郵送でお申し込み下さい。(申込書のページをそのままご送付下さい。)
http://www.asj.gr.jp/lecture/2012/seminar20121101.pdf - 申込先:
日本音響学会事務局 〒101-0021 東京都千代田区外神田 2-18-20
ナカウラ第5ビル2階
Tel. 03-5256-1020
‘その他の催し’ カテゴリーのアーカイブ
日本音響学会第122回技術講習会「Praat による音声加工と知覚実験の実施法」講習会
第22回Japanese/Korean Linguistics Conference (お知らせおよび発表募集)
発表の応募締め切りは、2012年5月15日です。詳細については、jk2012[at]ninjal.ac.jp までお問い合わせください。
| Date: | October 12-14, 2012 |
| Place: | National Institute for Japanese Language and Linguistics (NINJAL) |
| Website: | http://www.ninjal.ac.jp/jk2012/ |
| Contact: | jk2012[at]ninjal.ac.jp |
早稲田大学公開講演会「単一形態素名詞に基づいた苗字のアクセント」
| 日時: | 2012年2月4日(土)14:00~16:00 |
| 場所: | 早稲田大学早稲田キャンパス 22号館2階 202教室 |
| 講演者: | ティモシー・バンス氏(国立国語研究所教授) |
| 紹介者: | 原田哲男(早稲田大学教育・総合科学学術院教授) |
| 紹介: | 日本語音声学・音韻論の入門書として有名な『The Sounds of Japanese』(Cambridge University Press, 2008)の著者である Vance氏をお招きし、講演会を開催する。指導や学習に役立つ日本語の音の特徴について等、わかりやすくお話しいただく予定。 |
| 要旨: | 東京方言のアクセント体系は高低アクセントで、声の高さが比較的高いピッチから急に比較的低いピッチまで下がるのをアクセ ントの核と呼ぶ。内容語のアクセントは、語彙目録において指定されており、名詞の場合は、音節の数を n とすれば、アクセント型の可 能性は n +1 である。有核だとすれば、その核は音節のどれかに位置するが、もう1つの可能性は無核である。しかし、n 音節からなる名 詞の場合でも、可能な n +1 のアクセント型の割合が等しいわけではない。まず第一に、名詞の半分ぐらいは無核 (平板) である。そして 第二に、2モーラ以上の有核名詞の大多数は核の位置がデフォルト (後ろから3番目のモーラを含む音節) になっている。(2モーラしかな い単語は、語頭の音節がデフォルトの位置である。)東京方言のアクセント体系が、将来2型式に変遷すると予言してもこじつけではないで あろう。2型式の体系とは、核の有無だけが弁別的で、核があれば、位置が決まっているという体系を指す。九州の南西部や琉球諸島には 、2型式の体系が今でも多い。苗字は名詞の一種であるが、東京方言では、既に2型式のアクセント体系に従う。有核の苗字は、ほとんど 例外なく核がデフォルトの位置にある。単一形態素名詞に基づいた苗字は、数が少ないが、アクセントに特徴がありそうである。苗字のア クセントが普通名詞のアクセントに一致するケースがある(例の記載省略)しかし、一致しないケースもかなりある(例の記載省略)例か ら推定すると(1) 普通名詞が無核の場合は、苗字も無核。(2) 普通名詞が有核の場合は、苗字も有核で、普通名詞の核の位置にかかわらず 苗字はデフォルトの位置。残念なことに、この規則に当てはまらない苗字もある(例の記載省略)平板型の普通名詞が起伏型の苗字に対応 するケースが特に多い。アンケート調査によって上記の (1) (2) に当てはまる傾向が統計的にあるかどうかを調べてみた。本発表では、 その調査の結果を報告する。 |
| 総合司会: | 東京音声研究会代表 中川千恵子(早稲田大学)・木下直子(明海大学) |
| 共催: | 東京音声研究会 |
| 参加費(資料代): | 1人500円 |
| 使用言語: | 日本語 |
| 参加対象者: | 不問 |
| 事前申し込み: | 不要 |
| 問い合せ先: | 東京音声研究会事務局 大山健一(大東文化大学) |
| Email: | tokyo.onsei[at]gmail.com |
| URL: | http://wiki.livedoor.jp/tokyo_onsei/ |
Healey教授講演会「CALMS モデルによる吃音のアセスメントと臨床」
会場案内
各会場では、E. Charles Healey 教授の講演に併せて 以下の講演が行われます。| ◇広島会場 |
12月4日(日) 13:30~17:00(13:00開場) 広島大学教育学部 L205号教室 〒739-8524 東広島市鏡山1-1-1(広島大学総合博物館階上) (広島大学東広島キャンパス内) 川合 紀宗(広島大学) 「吃音の包括的・総合的アセスメントの重要性」 |
| ◇福岡会場 |
12月7日(水) 18:00~20:00(17:40開場) 福岡教育大学附属教育実践総合センター2階大III教室 〒811-4192 福岡県宗像市赤間文教町1-1 (福岡教育大学キャンパス内) 見上 昌睦(福岡教育大学) 「言語症状、環境調整、本人の反応にアプローチした学齢期吃音児の指導」 |
| ◇大阪会場 |
12月10日(土) 13:00~16:30(12:30開場) 大阪医療福祉専門学校 3階大教室 〒532-0003 大阪市淀川区宮原1-2-14 (大阪医療福祉専門学校内) 氏平 明(豊橋技術科学大学) 「吃音者と非吃音者の非流暢性の音声学・言語学的側面」 |
| お問い合わせ |
広島大学大学院教育学研究科附属特別支援教育実践センター 〒739-8524 東広島市鏡山1-1-1 TEL & FAX: 082-424-7179 Email: csnerp[at]hiroshima-u.ac.jp (担当:川合・大鹿) |
| その他 |
入場は無料です。事前予約も不要です 日本語通訳あり (当日は混雑が予想されますのでお早めにお越しくださいませ。全員分の座席 が確保できない場合もございます。何とぞご了承くださいませ) |
なお、詳細につきましては以下のPDFファイルをご覧ください。
| http://www.psj.gr.jp/jpn/documents/healey2011.pdf |
上智大学ORC 2011年度第1回研究会
上智大学オープン・リサーチ・センター ヒューマンコミュニケーショングループ
~2011年度 第1回研究会のご案内~
| 講演者: |
Keith Johnson先生 (Professor, Department of Linguistics, UC Berkeley) |
| タイトル: | Three Studies on Compensation for Coarticulation |
| 日時: | 2011年9月29日(木) 13 : 00 ~ 14 : 30 |
| 会場: | 上智大学 2号館 508号室 |
| その他: | 参加費:無料、参加申込:不要、使用言語:英語 |
| 主催: | 上智大学 オープン・リサーチ・センター 「人間情報学研究センター」 |
| URL : | http://www.splab.ee.sophia.ac.jp/~orc/ |
| 共催: | 上智大学女性研究者支援プロジェクト、日本音声学会 |
| お問い合せ先: | 上智大学 理工学部 情報理工学科 荒井隆行 (arai[at]sophia.ac.jp) |
日本音響学会第119回技術講習会 「音の心理学的測定法講座」講習会
http://www.asj.gr.jp/lecture/2011/seminar20111124.pdf
| 日時 |
平成23年11月24日(木)10:00~18:00 平成23年11月25日(金) 9:00~17:00 |
| 場所 |
東京大学生産技術研究所中セミナー室(総合研究実験棟4階) (東京都目黒区駒場4-6-1,小田急線/東京メトロ千代田線東北沢駅から徒歩7分, 又は京王井の頭線駒場東大前駅から徒歩10 分Tel.090-322-18530 当日の学会携帯電話) アクセスは以下の地図もご参照下さい。 駒場リサーチキャンパスへの地図: http://www.iis.u-tokyo.ac.jp/access/access.html 駒場リサーチキャンパス内配置図: http://www.iis.u-tokyo.ac.jp/access/campusmap.html |
| 参加費 |
正会員・賛助会員・協賛学会員 30,000 円 (※日本音声学会会員の皆様は協賛学会員に該当します) 学生会員 7,000 円 一般学生 8,000 円 会員外 40,000 円 定 員 60 名 |
| テキスト | 「音の評価のための心理学的測定法」(難波精一郎,桑野園子 著 (社)日本音響学会編(税込3,675円のテキスト代は参加費に含まれます。)他 |
| PC | 2日目にはソフトウェアを用いた実習を行います. 無線LAN機能の備わったノートパソコンをご持参下さい.可能な限り事前にR をインストールしてください。フリーソフトRは http://cran.r-project.org/ からダウンロードできます.原則としてWindowsを用いて講義しますが,Mac機や Linux機を持参しても構いません.その場合には事前にRをインストールしておいて下さい.なお,1日目の講習ではPCは必要ありません. |
| 申込期限 | 平成23 年11 月17 日(木) |
| 申込方法: |
下記の URL より申込用紙をダウンロードし,所定の事項を記入の上,日本音
響学会事務局までファクシミリ又は郵送でお申し込み下さい。(申込書のページをそ
のままご送付下さい。) http://www.asj.gr.jp/lecture/2011/seminar20111124.pdf |
| 参加費の納付 |
参加費は申し込みと同時に学会事務局宛郵便振替・銀行振込,又は現金書留にてご送金下さい。 ただし,学生会員及び一般学生は会場受付で納入されてもかまいません。なお,お支払いにあたり請求書を必要とされる場合は,申込書の「請求書要」欄にチェックして下さい。 |
|
協 賛 (依頼予定) | 日本建築学会,日本騒音制御工学会,日本機械学会,自動車技術会,日本音声学会, 日本音声言語医学会,日本音楽知覚認知学会,日本心理学会,AES 日本支部 |
| 日本音響学会事務局 |
〒101-0021 東京都千代田区外神田2-18-20 ナカウラ第5ビル2階 Tel.03-5256-1020,Fax:03-5256-1022 |
| 郵便振替先 | 社団法人 日本音響学会 00120-9-136290 |
| 銀行振込先 |
口座名義はいずれも 社団法人 日本音響学会 三菱東京UFJ 銀行 新宿中央支店 普通預金3935498 三菱東京UFJ 銀行 神田駅前支店 普通預金1671112 三菱東京UFJ 銀行 秋葉原支店 普通預金3909748 みずほ銀行 新宿西口支店 普通預金1164066 三井住友銀行 神田支店 普通預金2175551 |
[公開シンポジウム] N型アクセントの原理と成立
東日本大震災の影響により延期されていた日本女子大学・国立国語研究所共催の公開シンポジウム「N型アクセントの原理と成立」は、このたび国立国語研究所主催の企画として、きたる5月21日(土)に、神戸大学で開催されることとなりました。
詳細は以下をご覧下さい。
[公開シンポジウム] N型アクセントの原理と成立
| 日時: | 2011 年 5 月 21 日 (土) 13:00~17:30 |
| 場所: |
神戸大学文学部C棟 361会議室 (神戸市灘区六甲台町1-1) |
| 内容 |
|
| 問い合せ先: |
国立国語研究所 木部暢子 Email: nkibe[at]ninjal.ac.jp |
|
参考: 公開シンポジウム「日本語アクセント記述研究の現在」の開催延期について(2011/3/16) [公開シンポジウム] 日本語アクセント記述研究の現在(2011/2/25) |
公開シンポジウム「日本語アクセント記述研究の現在」の開催延期について
「日本語アクセント記述研究の現在:N型アクセントの原理と成立」
は,開催を 延期 させていただくこととなりました。
(なお、これに伴い、20日(日)に同じ会場で開催予定だった国立国語研究所 主催の研究発表会も、開催を延期させていただきます。)
ご参加予定の皆様には多大なご迷惑をおかけすることになり誠に恐縮ですが、 余震の可能性、それに伴う急な停電や交通機関の不通、等々、今後も不測の事態 が生じる可能性が無いとは言えない現状であることを考慮いたしました。 皆様、何卒ご理解、ご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。
なお、あらたな開催日時、開催場所等につきましては,決定し次第、おって お知らせいたします。 今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
世話人:松森晶子(日本女子大学) matumori[at]fc.jwu.ac.jp
早稲田大学公開講演会「単一形態素名詞に基づいた苗字のアクセント」
| 日時: | 2011年 3月 12日 (土) 14:00~16:00 |
| 場所: | 早稲田大学早稲田キャンパス 22号館2階 201教室 |
| 講演者: | Timothy J.Vance(国立国語研究所教授) |
| 紹介者: | 原田哲男(早稲田大学教育・総合科学学術院教授) |
| 要旨: | 東京方言のアクセント体系は高低アクセントで、声の高さが比較的高いピッチ から急に比較的低いピッチまで下がるのをアクセントの核と呼ぶ。内容語のア クセントは、語彙目録において指定されており、名詞の場合は、音節の数をn とすれば、アクセント型の可能性は n +1 である。有核だとすれば、その核は 音節のどれかに位置するが、もう1つの可能性は無核である。しかし、n 音節か らなる名詞の場合でも、可能な n +1 のアクセント型の割合が等しいわけでは ない。まず第一に、名詞の半分ぐらいは無核 (平板) である。そして第二に、 2モーラ以上の有核名詞の大多数は核の位置がデフォルト (後ろから3番目のモー ラを含む音節) になっている。(2モーラしかない単語は、語頭の音節がデフォ ルトの位置である。)東京方言のアクセント体系が、将来2型式に変遷すると予 言してもこじつけではないであろう。2型式の体系とは、核の有無だけが弁別的 で、核があれば、位置が決まっているという体系を指す。九州の南西部や琉球 諸島には、2型式の体系が今でも多い。苗字は名詞の一種であるが、東京方言で は、既に2型式のアクセント体系に従う。有核の苗字は、ほとんど例外なく核が デフォルトの位置にある。単一形態素名詞に基づいた苗字は、数が少ないが、 アクセントに特徴がありそうである。苗字のアクセントが普通名詞のアクセン トに一致するケースがある(例の記載省略)しかし、一致しないケースもかなり ある(例の記載省略)例から推定すると(1) 普通名詞が無核の場合は、苗字も無 核。(2) 普通名詞が有核の場合は、苗字も有核で、普通名詞の核の位置にかか わらず苗字はデフォルトの位置。残念なことに、この規則に当てはまらない苗 字もある(例の記載省略)平板型の普通名詞が起伏型の苗字に対応するケースが 特に多い。アンケート調査によって上記の(1) (2) に当てはまる傾向が統計的 にあるかどうかを調べたみた。本発表では、その調査の結果を報告する。 |
| 総合司会: | 東京音声研究会代表 中川千恵子(早稲田大学非常勤講師) |
| 共催: | 東京音声研究会 |
| 参加費(資料代): | 200円 |
| 使用言語: | 日本語 |
| 参加対象者: | 不問 |
| 事前申し込み: | 不要 |
| 問い合せ先: | 東京音声研究会事務局 大山健一(早稲田大学大学院) |
| Email: | tokyo.onsei[at]gmail.com |
| URL: | http://wiki.livedoor.jp/tokyo_onsei/ |
[公開シンポジウム] 日本語アクセント記述研究の現在
日本女子大学文学部・文学研究科 学術交流企画
[公開シンポジウム] 日本語アクセント記述研究の現在
「N型アクセントの原理と成立」
| 日時: | 2011 年 3 月 19 日 (土) 13:00~17:30 |
| 場所: | 日本女子大学目白キャンパス 新泉山館 1F 大会議室 |
| 内容 |
|
| 総合司会: | 坂本清恵(日本女子大学教授) |
| 共催: |
日本女子大学文学部・文学研究科 人間文化研究機構 国立国語研究所 |
| 備考: | このシンポジウムは、科学研究費補助金基盤研究(B) 「N型アクセントに関する総合的調査研究」の研究成果を発表するものです。 |
| 参加対象者: | どなたでも参加できます。 |
| 事前申し込み: | 不要 |
| 問い合せ先: |
日本女子大学文学部 松森晶子 Email: matumori[at]fc.jwu.ac.jp |
| URL: | http://www.jwu.ac.jp/grp/lecture_news/2010/20110319.html |